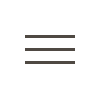〔ギター・マンドリン専攻特別講義〕パレルモ音楽院 教授 ダリオ・マカルーソ氏 マスタークラス
2025年10月14日に大阪音楽大学にて【ダリオ・マカルーソ氏 マスタークラス】が行われ、ギター・マンドリン専攻在籍生3名が受講した。
Dario Macaluso

ダリオ・マカルーソはパレルモのベッリーニ音楽院でクラシックギターを学び、1991年に最高の成績で卒業した。ウラディミール・ミクルカ、デイヴィッド・ラッセル、マヌエル・バルエコ、ロベルト・アウセルに師事したギター上級コース、グスタフ・レオンハルトとワルター・ファン・ハウヴェに師事してバロック音楽と現代音楽の解釈コースを受講。1994年から1998年にかけては、アムステルダムのスウェーリンク音楽院でレックス・アイゼンハルトに師事しギターと室内楽の研究を続け、最高の成績と特別表彰(アムステルダムのギター部門では前例のない成績)を得てUitvoerend Musicus(コンサート演奏ディプロマ)を取得して卒業。イタリアの多くの都市の音楽友の会、パレルモのマッシモ劇場、アントニオ・イル・ヴェルソ古代音楽協会、アムステルダムのベルラーヘ音楽院など、音楽協会や団体で演奏している。これまでに、ハーグのオランダ国会議事堂、レイキャビクのノルディック・ハウス、マドリードのソフィア王妃芸術センター、尼崎のヤマハ財団、東京の阿久寿ホール、音楽ホール、トリフォニーホール、サントリーホール、ハミルトン・プレイス・スタジオ・シアター、ダブリンのイタリア文化会館、京都、アムステルダム、ブエノスアイレスのボローニャ大学、アルゼンチンのロサリオ・メンドーサ大学、チリのサンティアゴ、ウルグアイなど、数多くの会場で演奏。2001年にはケンブリッジ大学でソロ・リサイタルを開催。ダブリンのモーストリー・モダン・シリーズ、カリアリのスパツィオ・ムジカ、アムステルダムのデ・アイズブレカーなど、著名な現代音楽祭やイタリアの様々なギター・フェスティバルに招待されている。東京音楽院、ダブリンのトリニティ・カレッジ、日本の様々な音楽協会、そしてイタリアの様々な機関や音楽院からマスタークラスを開講。パレルモ大学で古典文学を専攻し、音楽学の学位を優秀な成績で取得。クレメンティ、グァルニエリ、レッダ、コッコ、フォールフェルト、ソッリマ、ガラウ、ベッタ、ランダッツォ、ドワイヤーなど、数多くの作曲家の作品を初演し、献呈している。
プログラム
ソナチネより第三楽章(M.トローバ)
どの音に向かっているのかを意識するようにアドバイスした。また意図しないアクセントを注意した。和音をばらして弾く際にメロディーとなる音が良く聴こえるように指摘し、どう解釈してどう弾くべきかについて考えることの重要性を説明した。テンポ・ルバートを行う部分と拍子をはっきり捉えて弾く部分を弾き分け、メリハリをつけることにも言及した。
ソナタより第一楽章(M.ジュリアーニ)
音色について指摘があった。単音のみなら美しい音が出せるのに曲を弾くとタッチが変わることが惜しいので今後の課題として伝えた。また消音について言及があった。ギターは発音後、基本的に音が残るのでそれらをどの程度消音するべきか例を挙げながら説明した。休符の指示がない部分でもベースを消音することでメロディーが明確に聴こえるようになるのではないか、と提案し曲中の一部分を取り上げ具体的に述べた。
ワルツ第四番(A.バリオス)
全体的に大変素晴らしいので好みの範囲で説明すると伝え、いくつか提案した。音色や強さなどのタッチ、またフレーズの解釈、フレーズの中にアクセントつけると印象がどのように変わるのかを目の前で提示し、演奏のアイデアを紹介した。
三重奏Op.42より第一楽章(A.ロイエ)
それぞれのパートで目立つべき所がどこなのかを指摘。オーケストラを意識したものと考えて、もしバイオリンを意識していたとしたらもっとレガートに弾くべきではないかという指摘があった。もっと歌って弾くべきだという箇所を実際の演奏例で示した。
まとめ
学生にとって初めての英語によるレッスンだったが、マカルーソ氏が言葉を選び、表現をシンプルに伝えてくれたので特に通訳がなくてもおおよそ理解できた。事前に用意した質問に答えて頂き交流を行った。短い時間ではあったが大変有意義な時間となった。

Report / 大西洋二朗(本学講師)