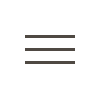〔ギター・マンドリン専攻特別企画〕客員教授・大萩康司氏による公開レッスン
2025年7月17日に大阪音楽大学にて【客員教授 大萩康司氏による公開レッスン】が行われた。
例年在学生に対して行われている大萩先生による特別授業で、今回は高校生の受講生と聴講生を一般で募集した。在学生3名、高校生3名、そして約35名の聴講生を前に公開レッスンが行われた。
例年在学生に対して行われている大萩先生による特別授業で、今回は高校生の受講生と聴講生を一般で募集した。在学生3名、高校生3名、そして約35名の聴講生を前に公開レッスンが行われた。


大萩先生は「演奏会を想定した弾き方」に重点を置いていた。長年第一線で活躍してきた演奏家だからこそできるレッスンで、「目から鱗が落ちた」という感想が多数あった。また聴衆に寄り添う音楽表現も特筆すべき点で、「作曲家」「聴き手」「演奏者」などあらゆる視点から音楽を解釈し演奏に反映する姿勢は大萩先生の音楽観を表していた。


以下レポートするが、記載内容はレッスンのほんの一部にすぎず、演奏実例も多かった。目の前で演奏を見て、聴くことは何よりも説得力のあるものだった。公開レッスンを受講することの面白さについて「先生の言われたことを目の前ですぐに再現できるか」「自分の持っている演奏方法の数を確認する場であり、新たな方法を得る場となる」と述べた。
自分を見つめ直し何か変化するきっかけとなり、学生にとって大変有意義な時間となった。
自分を見つめ直し何か変化するきっかけとなり、学生にとって大変有意義な時間となった。
在学生のレッスン
アラビア風奇想曲(F.タレガ)
グリッサンドして正確に目的の場所を押さえる方法や自然なアッチェレランドの方法について説明した。「間違える記憶を残さない練習」についても触れ、練習時間を効率よく使う方法を紹介し、頭の使い方がいかに大事かということについても言及した。
ワルツ第4番(A.バリオス)
曲のイメージをより明確にし、「アーティキュレーション」や「どの音を強調するのか」など細かく考えて表現する重要性を伝えた。場面変化の多い曲で弾き方の変化が求められる曲なので歌い方のニュアンスのバリエーションを多く持っておくと良いとアドバイスした。
アランブラの思い出(F.タレガ)
トレモロ奏法について技術的に気をつけることをいくつか紹介した。リズムでは表現できない「間」を作るのにフレーズを意識し、呼吸で表現する方法を説明した。また調性の変化から音色の変化についても言及し、実際にどのように雰囲気が変わるのか演奏した。
三重奏Op.12(F.グラニャーニ)
パートによる音量バランスについて言及した。ハーモニーの一部を弾いている場合は客観的に聴きバランスを調整することを伝えた。また和声の変化についてある程度共通した認識を持って音色・音量などを工夫することを説明した。
高校生のレッスン
基礎練習と音色の豊かさについて
(公開レッスン直前に手をケガしてしまったので)日頃の右手、左手の基礎練習を紹介した。また音色の豊かさについて知りたいという質問に対して「まずはイメージを持つこと」と答えた。それだけで一音目のタッチが変わることを説明し、いくつか例を提示した。技術的には極端な音色を出してみること、沢山の「実験」を通して音色の幅を広げてみると良いとアドバイスした。
ハンガリー幻想曲(J.K.メルツ)
発想記号から意図を読み取り、分かりやすく聴衆に伝えることに重点を置くように伝えた。曲想の変化が多い曲なのでより「指揮者」になったつもりで曲に取り組むと自分のイメージを固めることができると説明した。
BWV1000 フーガ(J.S.バッハ)
右手の運指次第で軽やかなトリルが弾けることを紹介した。また、終止感を出すフレーズの弾き方について言及した。テーマの弾き方を演奏により提示し、フーガの弾き方を分かりやすく説明した。
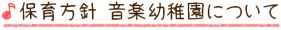
Report / 大西洋二朗(本学講師)